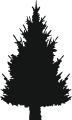SDGs視点で選ぶ家具一枚板テーブルのサステナビリティ
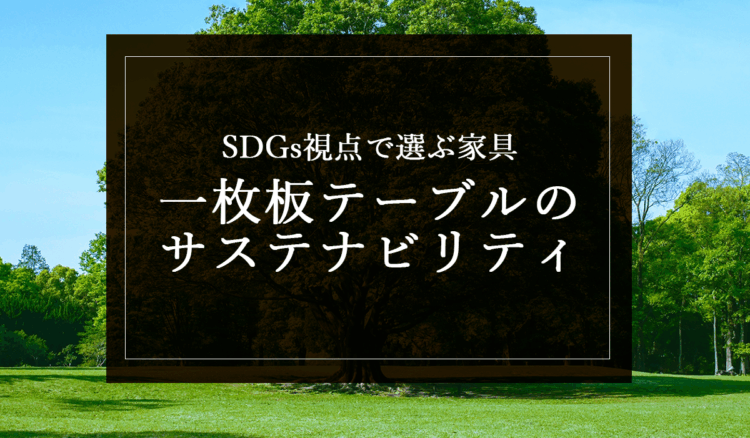
近年、持続可能な社会の実現を目指す「SDGs(持続可能な開発目標)」への関心が高まる中で、私たちの暮らしを彩る「家具」にも、その視点が求められるようになっています。中でも、無垢材を使った一枚板テーブルは、見た目の美しさだけでなく、地球環境への配慮や長期的な使用という点でも非常に注目されています。
本記事では、SDGsの視点から見た一枚板テーブルの魅力とサステナビリティについて、詳しくご紹介します。
1. SDGsとは?家具との関係を考える

まずはSDGsについて簡単におさらいしましょう。
SDGs(Sustainable Development Goals)は、国連が2015年に採択した「持続可能な開発目標」です。2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットが設定されており、環境・経済・社会のバランスをとりながら、より良い未来を実現しようという取り組みです。
家具とSDGsの関係として特に関わりが深いのが以下の目標です。
- 目標12:つくる責任 つかう責任
- 目標13:気候変動に具体的な対策を
- 目標15:陸の豊かさを守ろう
つまり、環境に優しい素材選びや、長く使える家具を選ぶことが、SDGsへの貢献につながるというわけです。
2. 無垢材・一枚板テーブルがサステナブルな理由
一枚板テーブルがSDGsの視点で高く評価される理由は、単なる「自然素材」であることにとどまりません。以下のような要素が、サステナブルな家具としての価値を高めています。
2-1. 天然素材だからこそ、環境負荷が少ない
無垢材とは、合板や集成材のように接着剤を用いず、天然の木そのものを使った素材のこと。一枚板はその名の通り、一本の木から切り出された板で作られます。
合成素材や大量生産型の家具に比べて、化学物質の使用が少ないため、製造過程での環境負荷が低く抑えられます。また、廃棄時にも自然に還りやすく、焼却しても有害物質を出しにくい点が魅力です。
2-2. 長寿命=廃棄を減らす
無垢の一枚板は、非常に頑丈で耐久性が高いため、数十年〜100年単位での使用も可能です。適切なお手入れをすることで、世代を超えて使い続けられる「資産」となる家具です。
これはSDGsの「つかう責任」に直結する考え方であり、「すぐ壊れて捨てられる家具」とは真逆の、真にサステナブルなプロダクトだといえるでしょう。
2-3. 修復・再生ができる
一枚板は、傷がついたり塗装が劣化したりしても、削って再塗装することで再生が可能です。これもまた、長く使い続けるための重要なポイントです。
最近では、オイル塗装など環境に配慮した仕上げも多く選ばれており、メンテナンスも比較的容易になっています。
3. 森林との共生:「適切な伐採」と「地域材」の選択

木を使うという行為は、「森林を減らすのでは?」という疑問を抱かれる方もいるかもしれません。しかし、これは一部の誤解でもあります。
3-1. 適切な伐採は森林を守る
日本の森林は、戦後に植林された人工林が成長しすぎて手入れが追いつかず、「森林の高齢化」が進んでいます。適切に間伐・伐採し、使うことで森林の循環を促し、生態系の健全化にもつながるのです。
つまり、木を使わないことが必ずしもエコではなく、「正しく木を使う」ことが重要なのです。
3-2. 地域材を使うという選択
輸入木材ではなく、国産の地域材を選ぶことで、輸送時のCO₂排出削減や地域経済への貢献といったメリットも生まれます。
たとえば、岐阜県の東濃ヒノキ、北海道のミズナラ、九州のクスノキなど、地域ならではの木を選ぶことで、その土地の文化や森林保全にもつながります。
4. 廃棄ゼロを目指す家具選び
SDGsの中でも注目されているのが「ゼロウェイスト(廃棄ゼロ)」の考え方です。一枚板テーブルは、この考え方にも非常にマッチします。
4-1. 廃材の活用や端材のリメイク
一枚板のテーブルは、製作時に余った木材や切り落とし部分、いわゆる“端材(はざい)”が出ることもあります。しかし、この端材が無駄になることはほとんどありません。多くの木工職人や家具工房では、こうした端材を活かして、小物やアクセサリーなどのリメイク製品を制作しています。たとえば、カッティングボード、コースター、文具トレイ、時計フレーム、スマートフォンスタンド、さらにはアートパネルなど、アイデア次第で多様な製品に生まれ変わるのです。
このように、端材を有効活用する取り組みは、木を使い切るという意味でとても重要ですし、“ゼロウェイスト”の実現にも直結します。SDGsの観点から見ても「つくる責任・つかう責任(目標12)」を実践する素晴らしい事例だといえるでしょう。また、端材を使ったアイテムは一つひとつが異なる木目や色合いを持ち、小さくても**“唯一無二”の存在感**を放ちます。そういった製品を手にすることで、素材の大切さや職人の手仕事への敬意を自然と感じることができるのです。
4-2. リユース・リペア・リフォーム
無垢の一枚板テーブルは、その構造が非常にシンプルであるがゆえに、リユース(再利用)やリペア(修理)、そして**リフォーム(再加工)**といった対応がしやすい家具です。たとえば、天板の表面に傷がついた場合でも、再研磨と再塗装でまるで新品のように美しく蘇らせることができます。これは合板や化粧板では難しい点であり、無垢材ならではの大きなメリットです。
また、ライフスタイルの変化に合わせて、サイズを調整したり、脚を付け替えて高さを変えたりといったパーツ単位でのリフォームも可能です。天板だけを再利用して、ベンチやデスクに変えるというような応用もできるため、廃棄せずに長く使い続けられる点で非常にサステナブルです。
さらに、質の高い一枚板テーブルは中古市場でも人気があり、**リユースされることで新たな家庭へと“引き継がれる家具”**になります。これは「循環型社会」の実現に向けた重要なステップであり、無垢家具の大きな強みでもあります。まさに、「モノを大切に使い続ける」ことが、環境にも人にもやさしい未来につながるのです。
5. ライフスタイルとともに育つ家具

一枚板の魅力は、見た目や環境性能だけではありません。**「暮らしとともに味わいを増す」**という、唯一無二の魅力があります。
5-1. 経年変化を楽しむ
無垢の一枚板テーブルの最大の魅力のひとつが、経年変化です。家具というのは通常「買ったときが一番キレイ」と思われがちですが、一枚板は違います。時が経つほどに木の表情は豊かになり、色合いも深みを増していきます。これは、木が生きていた証であり、呼吸する素材だからこそ起きる変化です。たとえば、ナラ材は黄味がかったブラウンに、ウォールナットは濃いブラウンからやや赤みがかっていくなど、それぞれの木が持つ個性が年月とともに浮き彫りになります。
また、光の当たり方や置かれる環境によっても変化は異なり、世界に一つだけの“育った木”としての表情が刻まれていきます。この変化を「劣化」ととらえるのではなく、「味わいが増す」と楽しめるのが、自然素材を選ぶ豊かさです。買った瞬間から完成するのではなく、暮らしの中で完成していく家具。それが無垢の一枚板テーブルの本質なのかもしれません。
5-2. 家族の記憶を刻むテーブル
一枚板のテーブルは、ただの家具ではなく、家族の記憶を重ねていく場所でもあります。食事を囲む、子どもが宿題をする、お祝いごとで乾杯を交わす…そんな日常の風景が、無垢の天板の上に少しずつ“記憶”として積み重なっていくのです。子どもが落書きをしてしまったり、誰かがうっかりコップの跡をつけてしまったり──そうした傷さえも、思い出として残せるのが無垢材の懐の深さ。
また、長年使い込むことで愛着が湧き、「このテーブルと共に育った」「このテーブルで大事な話をした」といった物語が家具に宿るようになります。引っ越しやリフォームのたびに買い替える家具では得られない、**“人生とともに歩む存在”**としての価値があるのです。そして、そのテーブルが親から子へ、子から孫へと受け継がれていけば、それはもう“家具”というより、家族の一部ともいえるでしょう。一枚板だからこそ、それが可能になるのです。
6. 未来のために、私たちができる選択
家具を選ぶという行為は、単なるインテリア選びではありません。**「どんな未来を選ぶか」**という意思表示でもあります。
無垢の一枚板テーブルは、
- 長く使える
- 修復できる
- 地球に優しい
という観点から、まさにSDGs時代にふさわしい家具のあり方を体現しています。
安価で大量生産された家具を短期間で使い捨てる時代から、**一つの家具を愛着を持って長く使い続ける時代へ。**その象徴とも言えるのが、一枚板の無垢テーブルなのです。
まとめ:サステナブルな暮らしに、一枚板という選択を
一枚板の無垢テーブルは、美しさ・耐久性・環境への配慮、そして「使い捨てない価値観」のすべてを兼ね備えています。まさに、SDGsの目指す未来と親和性の高い家具と言えるでしょう。
自然とともに生きる。
モノを大切にし、世代を超えて受け継ぐ。
その考え方こそが、持続可能な社会をつくる第一歩です。
あなたの暮らしに、サステナブルな一枚板を取り入れてみませんか?
当社の製品はオンラインでご依頼いただけます。
通販サイトはこちらから