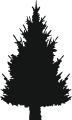一枚板は資産になる?10年後も価値が落ちない家具の条件
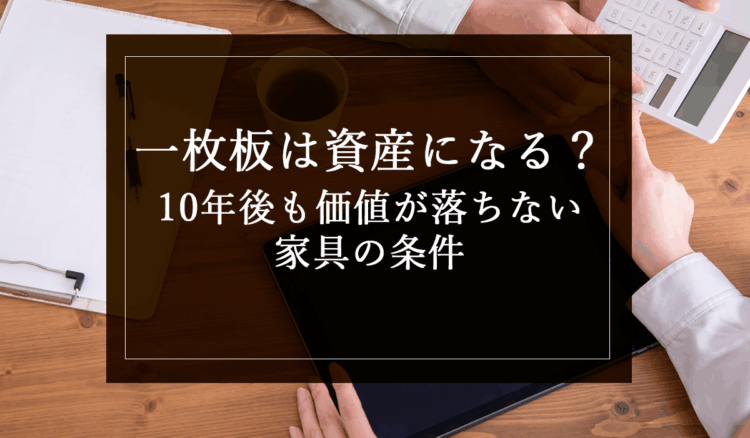
家具は「消耗品」と思われがちですが、一枚板のテーブルに限ってはその概念が当てはまりません。
無垢の木を丸ごと一枚使い、職人が丹念に仕上げたテーブルは、年月とともに味わいを増す育つ家具です。
10年経っても、20年経っても、その存在感と美しさは失われるどころか、むしろ深みを増していきます。
そんな一枚板は、単なる“家具”ではなく、「資産」としての価値を持ちうる存在。
なぜなら、木材そのものが持つ希少性や、職人の手による一点物の価値、
そして再生可能な素材としての強みが、時間とともに価値を積み上げていくからです。
本記事では、「一枚板はなぜ資産になるのか?」そして「10年後も価値を落とさない家具の条件とは何か?」を、
木の専門家と職人の視点から掘り下げてご紹介します。
将来にわたって愛着を持ち、家族の歴史とともに育てていける“資産家具”の本質を、一緒に見ていきましょう。
1. 一枚板が「資産」と呼ばれる理由とは

1-1. 木が「生き続ける」素材であること
無垢材は伐採された後も、呼吸を続けています。
季節の湿度や温度に応じて伸縮し、まるで人と共に生きているような存在です。
この“呼吸する素材”という性質が、経年による変化を劣化ではなく「味わい」へと変える大きな要因。
人工素材のように剥がれや変色が起こることもなく、
小さな傷やシミも削って再塗装することで新品同様に蘇る。
この「再生可能な素材」という特性が、一枚板を資産と呼べる大きな理由です。
また、年月とともに色味や艶が変化していくことで、
世界に二つとない表情を生み出していく。
つまり一枚板は「時間」と「暮らし」によって価値を熟成させていく素材なのです。
1-2. 希少な樹種とサイズがもたらす希少価値
幅広で節の少ない一枚板は、一本の大木からわずかにしか取れません。
なかでもウォールナット・モンキーポッド・楠(くす)・欅(けやき)・栃(とち)などは、
美しい木目と強度を兼ね備え、世界的に人気の高い銘木です。
近年、森林資源の保護や輸出制限などにより、これらの材の市場供給量は減少傾向。
つまり、自然素材としての希少性が年々上昇しているのです。
この背景から、良質な原木を確保して製材できる職人や工房は限られ、
一枚板はますます「手に入りにくい存在」へと変わりつつあります。
「量産できない」ということは、価値が時間とともに下がりにくいということ。
まさに、天然資源としての木材そのものが“資産と言えるのです。
1-3. 職人の手による「工芸品」であること
同じ木でも、仕上げる職人によってその表情はまったく異なります。
木目を活かす削り方、磨き方、塗装の厚み——それらの全てに職人の経験と感性が宿ります。
来宝綜合銘木工業では、熟練の職人が一枚ずつ状態を見極め、
鉋(かんな)で丁寧に木肌を整え、木そのものの呼吸を損なわない仕上げを施しています。
このような手仕事は、単なる家具づくりを超えた工芸の領域です。
職人の技術は時を経ても評価され続けるものであり、
作り手の存在が価値を支える「無形資産」として残るのです。
2. 10年後も価値が落ちない家具の条件

2-1. 素材の「質」を見極めること
資産価値を維持できるかどうかは、まず素材の選定にあります。
目の詰まった柾目の材、反りや割れの少ない板、そして適切に乾燥させた木。
これらの条件を満たす一枚板は、時が経っても変形しにくく、長く安定した美しさを保ちます。
木材は天然のものゆえ、一本ごとに個性が違います。
来宝では原木の段階から状態を見極め、含水率の管理を徹底。
「素材の質」に妥協しない姿勢こそ、10年後も輝く家具を生み出す基盤です。
2-2. 適切な乾燥と管理による安定性
木材は乾燥が命といわれます。
十分に乾燥されていない板は、設置後に反りや割れが発生することがあります。
そのため、自然乾燥と人工乾燥を組み合わせたハイブリッド乾燥が重要になります。
自然乾燥で木の個性を活かしつつ、人工乾燥で内部の水分をコントロール。
これにより、含水率が安定し、使い始めてからの変形を最小限に抑えられます。
この工程を怠ると、10年どころか数年で劣化が進むこともあるため、
「乾燥」は一枚板の寿命を決定づける最も重要なステップといえるでしょう。
2-3. メンテナンスが容易であること
価値を長く保つ家具には、「手入れのしやすさ」も欠かせません。
ウレタン塗装のように表面を完全に覆う仕上げは、メンテナンスが難しく、
一度傷がつくと部分補修ができません。
その点、オイル仕上げは小さな傷や水シミも自分で補修でき、
布やスポンジでオイルを塗り重ねるだけで艶が戻ります。
こうした“育てる楽しみ”が、愛着とともに資産価値を高めるのです。
また、定期的にワックスを塗ることで汚れの付着を防ぎ、
木の呼吸を保ちながら長期にわたって美しさを維持できます。
3. 経年変化を楽しむという「価値の成熟」

3-1. 年月が生み出す深みと艶
一枚板は、年月とともに色合いが深まり、表面に艶が生まれます。
ウォールナットなら深いチョコレートブラウンに、
ナラやタモなら飴色に、栃なら優しい乳白色から黄金色へと変化。
光の当たり方によっても印象が変わり、「経年美」が暮らしに豊かさをもたらします。
この変化は人工的に再現できないもので、
「古くなる=価値が落ちる」ではなく、
「古くなる=価値が育つ」ことを実感できる稀有な家具です。
3-2. 傷やシミが“物語”になる
家族とともに過ごした年月の中でついた小さな傷や輪染み。
それはマイナスではなく、むしろ思い出として刻まれるものです。
リビングで子どもが描いた絵の跡、友人との食事でできたワインのシミ。
その一つひとつが、その家の歴史を物語ります。
無垢の木は、そうした跡を受け入れながらも、削れば再生できます。
つまり「使いながら成長していく家具」。
それが、一枚板が10年後も輝きを放つ最大の理由なのです。
4. 再生と循環が生むサステナブルな価値
4-1. 修復・再塗装による“第二の人生”
表面の汚れや傷を研磨し、再塗装すれば新品同様に蘇る——
これが一枚板の最大の強みです。
ウレタンからオイル仕上げへ変更したり、天板を再研磨して新たな表情を出すなど、
「再生」が容易なことが資産価値を支えています。
買い替えるのではなく直して使うという考え方は、
環境負荷の軽減にもつながり、サステナブルなライフスタイルを体現します。
4-2. 世代を超えて受け継がれる家具
かつての日本では、桐箪笥や欅の机を代々受け継ぐ文化がありました。
一枚板もまた、その精神を現代に受け継ぐ存在です。
メンテナンスを重ねることで、親から子へ、子から孫へと受け継ぐことができる。
これは単に“長持ちする家具”ではなく、家族の記憶を継ぐ資産なのです。
10年後も価値が落ちない家具とは、
「古くなっても捨てられない理由を持つ家具」だといえるでしょう。
5. 一枚板を「資産」として持つための実践ポイント
5-1. 信頼できる製材・仕上げ職人を選ぶ
木材の出所や乾燥履歴、仕上げ方法を明確に説明できる業者を選ぶことが大切です。
来宝綜合銘木工業では、製材・乾燥・仕上げ・販売までを一貫して管理しており、
トレーサビリティの確かな板だけを扱っています。
こうした背景の明確な一枚板は、購入後の資産価値を裏付ける大きな安心材料です。
5-2. 定期的なメンテナンスで育てる
1年に一度、オイルを塗り直すだけでも、木の表情は見違えるように蘇ります。
乾燥によるひび割れを防ぎ、表面の艶を保つためにも、
「年に一度のメンテナンス」を習慣にするのが理想です。
こうした手入れを楽しめる人ほど、一枚板を“資産”として育てられる人。
木と対話しながら長く付き合うその姿勢が、
結果として家具の寿命と価値を何倍にも引き上げます。
5-3. 設置環境を整える
直射日光が長時間当たる場所や、冷暖房の風が直接当たる位置は避けましょう。
急激な温度・湿度の変化は、木材の反りや割れを引き起こす原因となります。
理想は、風通しがよく湿度の安定した空間。
自然素材である木が心地よく“呼吸”できる環境を整えることで、
10年後も安定した状態を保つことができます。
【まとめ】「使うほどに価値が増す家具」を持つという贅沢
量産家具が「新品が最も美しい」とされるのに対し、
一枚板の家具は「使うほどに美しくなる」という真逆の価値観を持っています。
それは、木が生きているからこそ、そして職人の手が宿っているからこそ。
一枚板を資産として持つということは、
“高価なものを買う”ことではなく、“時間とともに成熟していく暮らし”を選ぶことです。
10年後も、20年後も、そのテーブルには家族の記憶と愛着が刻まれていく。
それこそが、来宝綜合銘木工業が提案する“一枚板の真の価値”なのです。
そのテーブルが、何十年、何百年も前から続く森の物語の一部であることを。
当社の製品はオンラインでご依頼いただけます。
通販サイトはこちらから